|
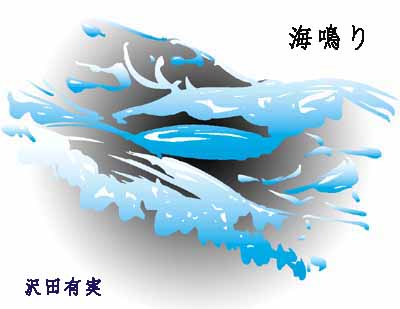
運良く就職が決まったのが、高校3年の最後の夏休み前。
就職活動と受験勉強に明け暮れる友人たちを尻目に、大介はバイトを入れた。
企業に入ってしまえばまとまった休みはそうそうとれるものではないから、学生
のうちに一人旅をしたかったのだ。
もちろん、自分の金で。
箱入り息子だったわけではないのだが、なかなか外泊も許してもらえず、当然、
旅費など出してもらえる当てなどなかった。
2学期、3学期と落第しない程度に学業をこなしバイトで金を貯め、卒業証書を
受け取ったその足で上野駅に立った。
もう着る事もなくなった制服は駅のゴミ箱に捨て、大介はディパックを背に夜行
電車に飛び乗ったのだ。
行き先は寒い所がいい。
身を切るほどに冷たい風の吹く、日本海がみたかった。
夜行を乗り継ぎたどり着いた港町は、1歩電車から降り立つと潮の香りがした。
ぼんやりとあたりを見回しながらディパックを足下に下ろすと、切符を買ったら
ほとんど残らなかった財布の中身にため息をついた。
「……帰りの旅費もないじゃん……」
歩いて帰るわけにも行かない。
大介は別にそれを苦痛に思うでもなく、表情を和らげた。
不安よりも期待の方が勝っている表情。
「バイト…どっかあるかなぁ…」
そういえば宿も決めていなかったと思い出し、大介はバイトの条件に項目を追加
する。
「住みこみのバイト」
くすくすと笑いながら。
足もとのディパックに空に近い財布を投げ込むと、大介は行く先もないままふら
りと足を踏み出した。
海が見たかったのだ。
潮の香りの強い方へと、大介は引き寄せられるように歩き出した。
楽しげに。
今にも走り出さんばかりに、軽い足取りで。
ふらふらと当てもなく歩いているうちに行き当たった灯台から見る海は、まだ夏
の青さには程遠く、どんよりと薄暗い色を浮かべていた。
岩に当たる波の激しさは、おなじような天候の東京の海と比べてもすさまじい。
「う、わ…落ちたら死ぬな…」
思わず言葉が口をつく。
「死ぬよ」
よもや独り言に返事が返ってくるとは思わなかったので、大介は慌てて声のした
方を振り返った。
「だっ!!!」
声の主は水平線の彼方を見ているかのようで、大介の事など気にもとめていない
ようだ。
ただ、風にさらわれるままにした髪が落ちて、日に焼けた顔にきらきらした瞳だ
けが印象的な少年だった。
「急に声かけられたら落ちるかもしれないだろ!」
大介が憤慨しながら、少年につめよると彼は腹を抱えて笑い出した。
「んだよ!?」
目尻に涙を浮かせながら笑いつづける少年は、第一印象と違って幼いものだった
。
「物好きだね」
初対面の人間にそんな事を言われて、大介はぽかんと口を開けた。
そんな大介の様子を見た少年は、言葉が足りなかったかと簡単に説明する。
「こんな時期にこの町に来るのは自殺者か物好きだけだよ」
後ろから声をかけらて落ちるかもしれないと怒るようなら、自殺志願者ではない
。
「悪かったな」
不機嫌そうに腕を組んだ大介は、ふと少年の容姿に目を止めた。
細身なのにしっかりとついた筋肉はスポーツで鍛えられたものとは少し違うよう
だ。
日に焼けた肌とばさばさの髪を遠慮なく見ていると、少年が顔をそむけるように
して言った。
「なんだよ…」
「おまえ…ドカタかなんかやってる?」
聞いた途端に少年は嫌そうな顔を浮かべた。
「なんでそんな仕事しなきゃなんねーんだよ!おれは猟師だよっ!」
「猟……師……?」
結局、大介は少年の家に世話になる事になった。
期限は一週間。
その頃には東京に戻らなくてはいけない。
少年は大介と同い年で、海人(かいと)と名乗った。
猟師の朝は早くて、大体3時くらいには起きだして船を出す。
「大変だな」と言ったら、子供の頃から父親の後を継ぐのを楽しみにしてたから
船に乗れるのが嬉しい、と言った。
「はぁ…」
「なに?疲れた?」
だらしがないなぁ、と笑いながら海人は舟のへりに手をかけた。
大介は否定するように顔の前で手を振ると、潮の香りを吸い込むように大きく深
呼吸した。
「気持いいなー、って」
やけに機嫌のよさげな大介を横目でみながら、海人は怪訝そうな表情を浮かべた
。
「あの…さぁ…」
「ん?」
「普段は…気持良くないわけ?」
海人が聞いているのが、東京での自分の生活の事だと気づいて大介は苦笑いを浮
かべた。
「東京の空気は澱んでるからなぁ……」
思い返すように呟くと、じっと海面を見ていた海人は考え込むように言った。
「よく…わかんないや…この海だって、子供の頃に比べれば澱んでる気がする…
」
その横顔がやけに寂しげで、大介は海人の頭を抱き寄せると子供をあやすように
ぱふぱふと肩を叩いた。
子供扱いするな、と口を開きかけて、思いなおしたかのように海人は体を大介に
預けた。
「澱んでるんだ…」
「そっか…そうだな…」
一週間はあっという間で。
大介が東京に帰る日、海人は泣いた。
顔をくしゃくしゃにしてぼろぼろ泣く姿が子供みたいだと思ったけれど、大介は
黙って海人を抱き寄せた。
「え…?」
抱き寄せられた事に一瞬驚いて、次の瞬間には海人は大介を突き飛ばしていた。
大介はやり場のなくなった手を宙に浮かせた半端な格好で苦笑いを浮かべていた
。
笑いを浮かべていてもショックは隠し切れなくて、洩らした小さなため息を海人
は聞き漏らさなかった。
「あ、違っ……!!」
慌てて大介の胸倉をつかみ、そのまま額だけを押し当てる。
「俺…涙とか鼻水でぐちょぐちょだから……その……」
服が汚れるから、と。
困ったように言い募る頭の間から覗く耳が赤い。
「海人…」
「………」
「顔、あげてよ」
「……やだよ…みっともねー顔してんもん……」
言いながらますます顔をうつむける海人の髪に唇を寄せる。
「…っ!!!」
ぴくりと身を震わせると、海人は慌てて顔を上げた。
「やっと俺のこと、見てくれた」
嬉しそうに笑う大介の顔が近づいてくるのを見ながら、海人も照れくさそうに笑
った。
触れるだけのキスをして。
大介は思い切って海人を東京に誘った。
海人は嬉しそうな顔を浮かべて、すぐに力なく首を振った。
「ダメ…」
「どうして?」
「俺は…海の傍でしか生きていけないから……」
悲しげに笑う海人を大介はきつく抱きしめた。
「大…介…苦しいよ…」
「……さ」
背中から聞こえたかすれ声に海人は耳を済ました。
「俺が来るよ…ここに……帰ってくる」
「………うん」
それだけで充分だった。
最後にきつく抱きしめると大介は海人に背中を向けた。
初めて会ったとき、きらきら輝く瞳が印象的だった。
繰り返し打ち寄せる波のリズムのように、少しずつ気持が近づいていくようで。
恋に落ちたんだと、気づいた。
「夏には…絶対、会いに来るから…」
東京へ向う列車の中、大介は遠ざかる海辺の町の空気を大きく吸いこんだ。
END
|